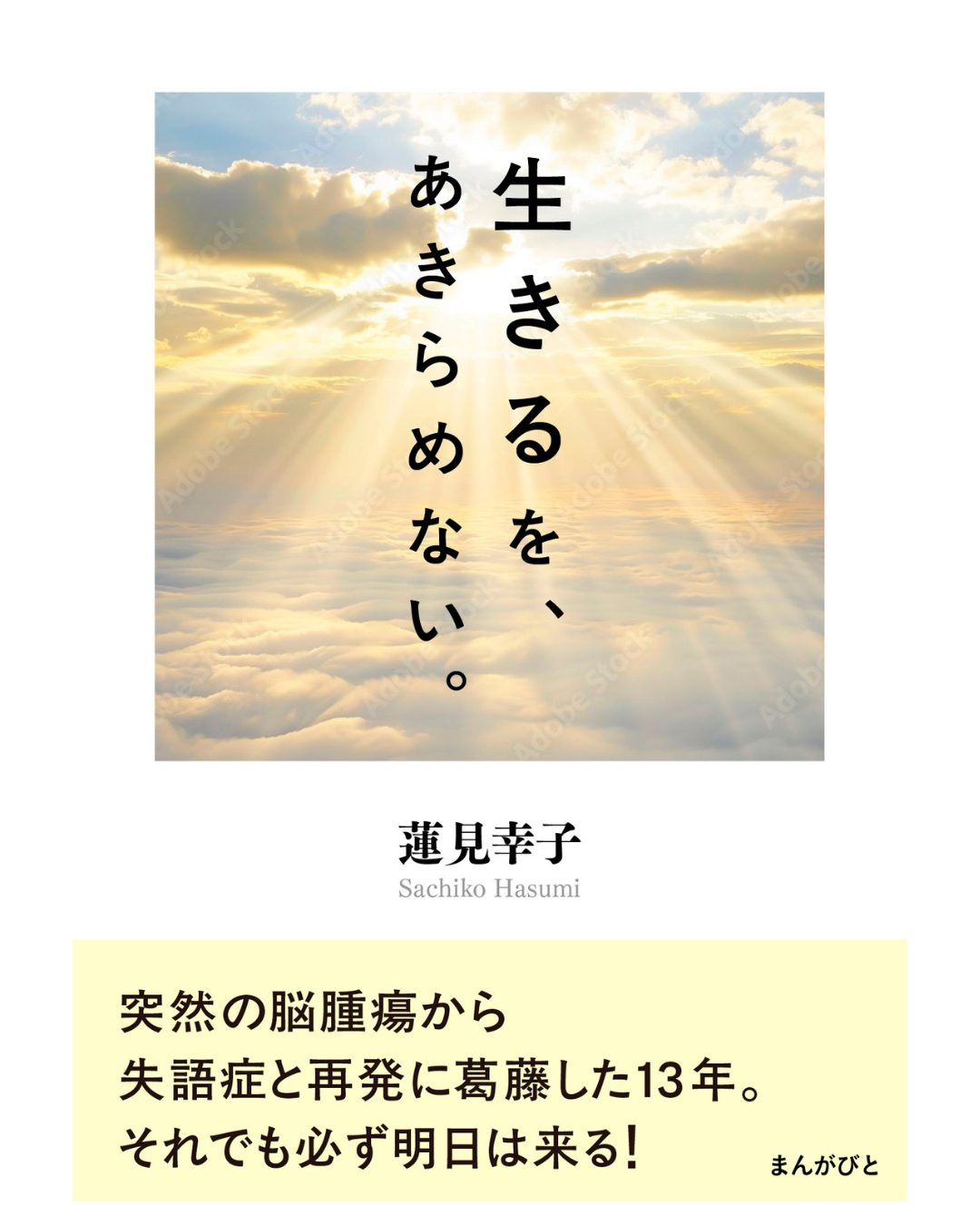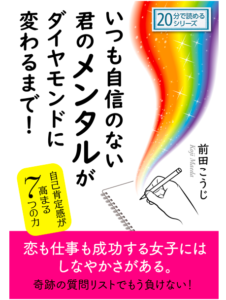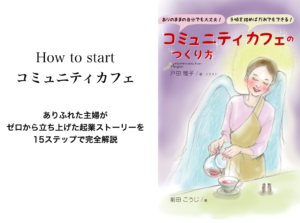現代は、生成AIの進化とともに僕たちの生活や働き方が大きく変わりつつある時代です。しかし、その便利さのウラには、人間本来の能力が失われていくという重大なリスクも潜んでいます。
天才科学者と呼ばれる苫米地英人氏は、近い将来登場するであろう人工超知能(ASI)をテーマに、私たちが直面する認知の変化や社会構造の大転換について語りました。
この記事では、同氏が語った内容を6つの視点から掘り下げて解説します。
1. 人間の「フィルタリング能力」の喪失
苫米地氏は、人間が本来持つ「不要な情報を無意識に除外し、必要な情報だけを抽出する力(認知フィルター)」が、外部のテクノロジーに委ねられることで弱体化していると指摘します。
たとえば、ノイズキャンセリング付きのヘッドホンを常用することで、騒音だけでなく他人の声や環境音まで遮断され、脳が自らフィルタリングする機能を働かせなくなっていくという現象が実際に起きています。
イギリスの研究では、そうした状況で育った若者が「言葉の聞き取り能力」に障害を感じるケースが増えており、これは情報処理力そのものの低下に直結します。
このようなツール依存は、長期的に見ると脳の可塑性を損ない、僕たちの認知能力に大きな悪影響を与えかねません。
2. AIが作る「情報のバブル」フィルターの外注がもたらす世界
AIによる情報提供は便利である一方で、個々人が接する情報の世界を極端に狭める危険性も秘めています。
苫米地氏は、「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」といった現象を総称して「インフォメーションバブル」と呼び、それがもたらす社会的孤立に警鐘を鳴らします。
たとえば、生成AIに質問して得られる答えは、個人の過去の検索履歴や興味関心に基づいて構築されたバイアスのかかったものです。隣の人と同じ質問をしても異なる答えが返ってくる可能性が高く、それぞれが別々の「現実」に生きるようになります。
これが社会的対話を困難にし、人間同士の認識のズレを広げていくのです。便利なはずのAIが、かえって世界の分断を深めているというパラドックスがここにあります。
3. 認知戦(Cognitive Warfare)AIが導く「思考誘導の戦場」
苫米地氏は、軍事戦略としての「認知戦」にも言及しています。これは単に敵を攻撃するのではなく、人々の思考・価値観・判断に介入する新たな戦争形態です。
AIは、個々人の思考や関心をモデリングし、その人に最適化された情報を提供します。これは軍事利用においては情報操作や心理誘導として応用され、現代の戦争は「情報」「サイバー」領域を超えて、「認知」にまで及んでいるのです。
たとえば、SNSでの操作によって特定の政治的意見が強化されたり、人々の選択行動が無意識に導かれるなど、私たちが気づかないうちにコントロールされている状況が起きています。
トランプ政権の台頭もこうした認知戦略の成功例とされ、今後は個人レベルでもこの影響から逃れることは困難になるでしょう。
4. 人工超知能(ASI)の登場と人間の「思考停止」
人工超知能(ASI)の実用化が目前に迫る中、苫米地氏はそれが人間の知的活動にどのような影響を与えるかを深く掘り下げます。
現在でも、GPTプロなどの生成AIを使えば、プロ並みの文章や資料作成が瞬時に可能です。実際、苫米地氏の会社の社員でも、AIに任せることで圧倒的な成果を出す人が増えているとのこと。
ところが、その一方で「思考する」という行為そのものが不要になることで、考える力が著しく低下しているのです。読めるけど書けない、聞けるけど考えられない・・・。そんな人が量産される未来が現実味を帯びてきています。
AIの進化はもはや個人の努力では太刀打ちできないスピードで進行しており、人間が「自分の頭で考える」機会は今後ますます減少する可能性があります。
5. 永遠の命と「デジタル人格」の未来
さらに苫米地氏は、人間の肉体的な制限からの解放、すなわち「永遠の命」の獲得という未来図も提示します。
脳の構造と認知モデルを完全にデジタル化し、30cm四方のデバイス内に記憶や人格を格納することで、肉体に依存しない存在が可能になるというのです。
実際、視覚や聴覚などの五感はすでに機械が人間を超える精度で再現できるようになっており、あとはそのインターフェースを脳にどう接続するかの問題です。
脳細胞を徐々に人工神経に置き換える技術が確立すれば、「自我の連続性」も保たれたまま、何百年も生き続ける人類が誕生します。これは単なるSFではなく、苫米地氏が実際に研究している領域であり、現実として起こり得る未来だとしています。
6. 人間の価値とは何か──AIが生み出せない「唯一無二性」
このようなAI万能の時代においても、すべての人が成功できるわけではありません。苫米地氏は、AIが代替できない領域として「アート」や「感性」、「個性」など、人間固有の表現に価値が宿ると述べます。
たとえば、どんなに技術的に優れた音楽家がいても、自分にとって特別なアーティストの歌声は、他では代替できない唯一無二のものです。この「代替不可能性」こそが、AI時代における人間の最大の強みとなるのです。
だからこそ、今後は「好かれる力」や「共感を呼ぶ表現力」など、いわば“人間くささ”が武器になる時代ともいえるでしょう。
すべてをAIに任せるのではなく、「人間にしか出せないもの」を追求する姿勢が、これからの社会において最も価値ある資産となっていくのです。
まとめ:人類は自由になるか、思考を失うか
苫米地氏が語る未来は、ある意味で「楽観的ディストピア」とも言えるものです。
AIによって死の恐怖から解放され、人間は“物理的に”自由になりますが、一方で「思考する力」「選び取る力」を失うことで、精神的・社会的には不自由になりうる。このような時代において重要なのは、AIを使いこなしつつ、自分の「フィルター」や「思考の軸」を持ち続けることだといえるでしょう。
情報引用元:苫米地英人の銀河系ゼミナール2025.4.1配信
CAIの使用で思考力低下―人工超知能(ASI)の功罪(https://www.youtube.com/watch?v=7nqOBY0BlYU&t=54s)